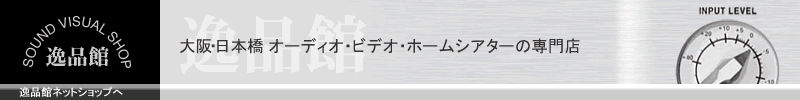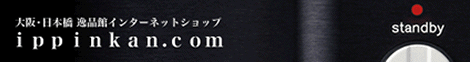| AIRBOWへ | 試聴機貸出 | 注文・見積もり | 買取 | 下取り交換 | メルマガ申し込み | カタログ請求 | お問い合わせ |
オーディオのパラドックス
原音再生を目指している製品が、メーカーによって音が違うのは何故か?
この世界には多種多様のオーディオメーカーが存在します。製品の音質に対するメーカーとしての要求を尋ねると、JBLだろうが、ALTECだろうがTANNOYだろうが、基本的に「High Fidelity」という答が返ってきます。世界最大のオーディオショウ・CESでいわゆる「High-End Audio」のメーカーに同様の質問をしても、全社判で押したように「Non Coloration」という答えが返って来るそうです。しかし、実際にそれらを聞いてみると、それぞれの製品の音は全く違います。何故、こんなおかしな事が起きるのでしょう?そこで、AIRBOWというオーディオ機器の設計者として私は、次のように考えています。
オーディオ機器から再現される音楽は、生演奏ではありません。オーディオ機器から再現される音楽は、いわば写真であり、絵画です。ありのまま、そのままを再現することは不可能なのです。
それ故に、「生演奏に忠実に再現を目指している」ことを、ある現場を撮影する、あるいは写生するということに置き換えると、同じ現場を写真にしても「写真家によって写し方が違う」ように、また写生するにしても「描き手」によって、「出来上がった絵が違う」ようにオーディオ機器から再現される音は違うのです。ですから、全てのメーカーが「原音忠実再生」を目指していて「全ての再生音」が違ったとしても、何ら矛盾はありません。
もちろん、作り手によって極端な色づけがなされることを好ましいとは思いません。しかし、色々な機器をよくお聞き頂ければ、評価の高い機器にはそれなりの「作り手の音楽的見識」がきちんと聞き取れるはずです。
その高度に洗練された「避けられない個性」には、「流儀」という表現がもっとも適切だと思います。音の違いは「流儀」の違いであって、「目指すもの=原音」がまるで違っているという事はないと思うのです。
つまり、オーディオの音をどこまで原音に近づけようとしても、結局は「未完成な機械の音」でしかなく、それに「命を吹き込み音楽として完成させる」ために「メーカーの音作り」あるいは「ユーザーの音作り」という「助け」が必要になります。そして、その「原音と再生音の差を埋める作業」こそが、オーディオマニアにとって「最終の謎」であり、「最大の問題(最大の楽しみ?)」となっているのは間違いありません。
音楽を聴くということ
私達の世界には「目に見えるもの」と「目に見えないもの」があります。例えば「友情」・「愛」などの「心の絆」は、目には見えませんが、その存在は誰もが知っています。「音楽」それも目に見えませんが、その存在は「普遍的」に誰もが認めます。しかし、この「目に見えないもの」は「目に見えるもの」とは違って、誰にでも同じように「見える=感じられる」訳ではなく、それは人の心のように「見ようとしなければ決して見えない」のです。
オーディオの聴き比べや評価をすり合わせていると、この「見える=音楽が聞き取れる」・「見えない=音楽が聞き取れない」の違いの大きさに愕然とさせられることがあります。極端なたとえ話になりますが「幽霊や霊魂」を見られたことはありますか?私には見えませんが、少数ながらそれらが見えるという人達がいます。もちろん「幽霊や霊魂」といった存在は、科学では証明されていません。では、「心」や「音楽」はどうなのでしょう?存在こそ普遍的に認められてはいますが、「幽霊や霊魂」と同じように、その存在は「科学的=定量的・定性的」には説明できないということでは同じなのです。少し乱暴なこじつけのようですが、完全に否定することもできないはずです。
では、これら「目に見えないもの」を見るために必要なものはどう言ったものなのでしょう?「感性」・「インスピレーション」そういったものも大切ですが、それは生まれつき備わっている感覚で、後天的に身に付くかどうかは疑問です。しかし、「幽霊や霊魂」と違って「心」や「音楽」は、そういった特別な感覚が生まれつき備わっている人だけでなく、「経験」・「知識」などの「それを見いだすために必要な要素」を意識して高めることで「より明確に感じ取れる(見える)」ようになります。そのため、程度の差はあっても「誰もがその存在を認められる」のです。
音から音楽を感じ取ることは、文章からその内容を把握するのに似ています。見えない情報の「送り手」と「受け手」に「共通する経験や知識」が多ければ多いほど、その内容が具体的に伝わります。その共通する「経験」や「知識」を「共通のチャンネル」と呼ぶことにしましょう。
文章は「文字」が、「音楽」は「音」が組み合わさってできています。文章の内容を正しく把握するためには「文章を並べ替えてその内容を解読する=読破力」が必要ですが、音楽を深く正しく聴き取るためにも同じ力が必要です。たとえれば、「音」で構成される「音楽というパズル」は、「虫食いパズル」のようなものです。「音」を正確につなぎ合わせ、虫食いの穴を埋めた時に、はじめて聴き手の心の中に「音楽」は姿を現します。
解くことさえ難しいこのパズルは、困ったことに「虫食いの穴が多ければ多いほど、伝わる内容が深くなる」という特徴を持っています。「文章」も「音(音楽)」も高度に省略されることで深みを持つのです。そして、意図的に高度に省略された「人的生産物」を我々は「芸術」と総称します。芸術を知り、音楽を聴くということは「音を通じてお互いの経験や知識を共有できる」ということです。その共有が成り立つ瞬間こそ「音楽を聴く喜びのすべて」だと私は感じています。ですから、私がオーディオに求める「音」とは、「その共有を成り立たせるために必要なパズルのピースの精度を損なわない」こと。そして、それを計るために重要なのが「演奏家と共通する感性のチャンネル」なのです。オーディオとは省略だと述べましたが、まさに「演奏をさらに芸術的に省略しなければならない」のがオーディオという技術なのです。
「パズルのピースの正確さ=音の精度」が音楽を感じるためにどれほど大切か?それをもっとも簡単かつ芸術的に表現できたのが、AIRBOWのヘッドホンシステムの音楽なのかもしれません。